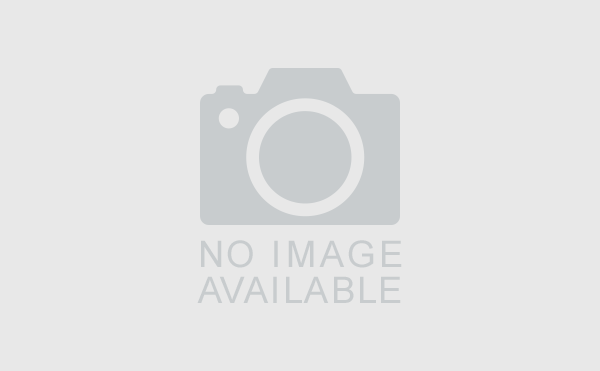寝違えについて
こんにちは。Emiです。
今回は、
〈寝違え〉について、お話ししていきます。
1. 寝違え
寝違えとは、朝起きたときに、首を動かすと痛い、振り向けない。
などの症状が出る状態をいいます。
多くの場合、睡眠中に、首や背骨の筋肉・関節が小さく損傷することで起こります。

2. 寝違えで損傷しやすい組織
寝違えのときにダメージを受けるのは、主に以下の2つです。
・首の筋肉
・背骨(頚椎)の関節
首を支える〈肩甲挙筋〉〈斜角筋〉〈板状筋〉〈胸鎖乳突筋〉〈僧帽筋〉などが、睡眠中に引っ張られ続けることで炎症や損傷が起きます。
3. 寝違えが起こる理由ー筋肉
睡眠中は筋肉がゆるみ、首を支える力が弱くなります。
このとき、不自然な姿勢で長時間寝ていると、頭の重さで、首の筋肉や血流に負担がかかり、筋肉が硬くなっていきます。
そして、朝の起き上がる動きなどで急に筋肉が引っ張られると、微細な損傷(炎症)が起き、寝違えになります。
4. 寝違えが起こる理由ー関節
筋肉だけでなく、首の骨同士をつなぐ椎間関節や関節包、靱帯なども損傷することがあります。
筋肉が弛緩している睡眠中は、関節は不安定になりやすく、首の動きの制御が効かなくなるためです。
5. 胸椎の動きと寝違えの関係
寝違えを引き起こす背景には、胸椎の硬さがあります。
胸椎の動きが悪いと、首や腰が代わりに過剰に動くようになり、首の安定性が低下します。
安定しない首は、寝ている間に頭の重さで引っ張られやすく、筋肉が常に緊張状態に。
その結果、朝の動き出しで損傷を起こしやすくなります。
6. 予防
寝違えを防ぐには、胸椎の可動性を高めることが重要です。
胸椎が、しなやかに動けば、首にかかる負担が減り、筋肉や関節の過剰な緊張を防ぐことができます。
また、首の土台となる胸椎が固まると、首の痛みだけでなく、椎間関節のズレや、筋肉の緊張などの悪循環を引き起こします。
7. 内臓や自律神経との関係
寝違えは、単なる筋肉や関節の問題だけではありません。
内臓の不調や自律神経の乱れによっても、筋肉の緊張や血流の悪化が起き、寝違えやすくなります。
8. まとめ
寝違えは、首の筋肉や関節の損傷に加え、胸椎の硬さ、自律神経の乱れも影響しています。
予防には、胸椎を柔らかく保ち、全身のバランスを整えることです。
しなやかな背中づくりが、寝違えに強い首を育てます。
良かったら参考にしてみてください(◕ᴗ◕✿)
Emi