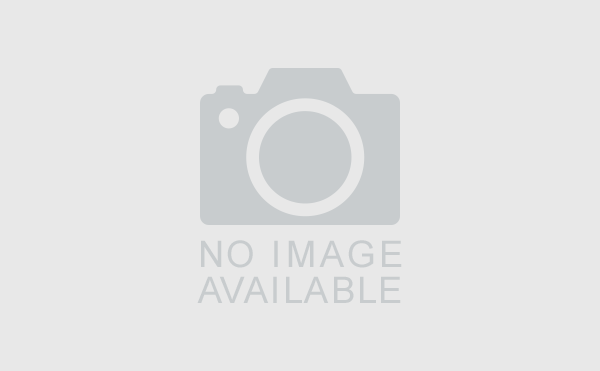内臓機能を高めよう!(胃・膵臓・脾臓)
こんにちは。Emiです。
今日は、「内臓(胃・膵臓・脾臓)」について
お話ししていきます。
内臓については、
過去のブログ<内臓について!>
で詳しくお話ししましたので、
詳細は、こちらをご覧ください。
1. 胃について
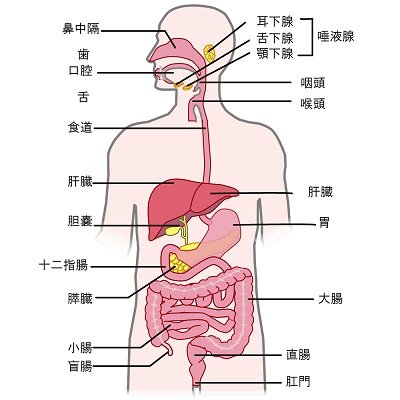
1-1 特徴
・主な働きは
胃液と蠕動運動による消化
①食べ物を一時的に貯蔵。
・病原菌などを殺菌
・熱いものや冷たいものの温度調整
をして腸へ送る
②胃液の分泌(1日に1.5~2.5ℓ)
・食物を見たり、匂いをかいだり、食物が胃に入ってきたりすることで、
その刺激を受けて、胃液が分泌され、食物が消化される
③食べ物を消化しやすいように粥状に(蠕動運動で胃酸と食べ物を混ぜる)
・胃には3層の筋肉があり、
伸び縮みして蠕動運動を行うことで、食物と胃液をかき混ぜる。
□胃粘膜→胃の内側を覆う粘膜層
・粘液→胃の内側を守る
・胃酸→食物を消化する
・消化酵素→食物を消化する
を分泌する
1-2 効果
・肩の痛み(左)
・坐骨神経痛(左)
・首の痛み(左)
・頭痛(左)
・胃下垂
・逆流性食道炎
・胃炎
・胃潰瘍
・慢性疲労(迷走神経)
1-3 幽門
◇幽門(胃の出口)の調整も!
幽門が開かないと、食べ物が小腸(十二指腸)に流れない
↓
胃に食べ物と胃酸が溜まる (中身が腐敗していく)
↓
消化不良・逆流性胃炎・口臭などの原因に
2. 胃に良いもの
■アロエが胃腸に良いとされる理由
・胃の粘膜を守って炎症を和らげたり、腸のぜん動運動を促進して便通を改善する作用があります。
・アロエの抗炎症・抗菌作用は、胃潰瘍や腸内環境のバランス改善にも役立ちます。
■食べ方
・胃腸の弱い人は、すりおろしたアロエがオススメ。
3. 膵臓について
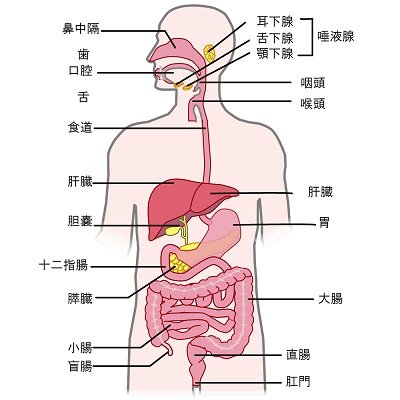
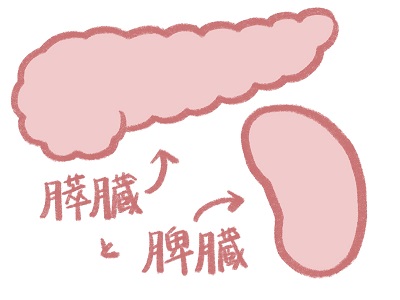
特徴
・長さは、約15cm
①消化酵素を分泌
・消化を助ける(消化酵素を十二指腸に)
◇糖質を分解
アミラーゼ
◇タンパク質を分解
トリプシン/キモトリプシン
カルボキシペプチターゼ
◇脂肪を分解
リパーゼ
②血糖値の調整
・血液中のブドウ糖の量を調整する
・膵臓の中心部:ランゲルハンス島がホルモンを分泌
↓
□グルカゴン→血糖値を上げる
□インスリン→血糖値を下げる
4. 脾臓について

特徴
・左上腹部の背中側よりある
・重さは、約120g
◆正常な血液を保つ!
・酸素を運べなくなった赤血球を壊す (3ヶ月が寿命)
・鉄分を取り出し骨髄に送る(新たな赤血球に使う)
・血小板(全体の1/3)の貯蔵庫
◆免疫機能
・体内で最大のリンパ器官とも言われる
5. お手当
・慢性化した病気の場合、脾臓は腫れて弱った内臓をカバーするので、脾臓は冷やすと良い。
・脾臓は、肝臓や腎臓とも関わりがある。
肝臓や腎臓は温めると良い。
◎まずは、温める!
↓
◇こんにゃく湿布
■やり方
①こんにゃく2丁を10分位ゆでる
②タオルに包む
③肝臓(右脇腹) と 丹田(おヘソの下)に置く
④30分位
(※温かさは1時間位続くが、もし冷めていたら温めなおす)
⑤温かいこんにゃくを腎臓(腰の上、背骨の左右にそれぞれ)に置く
⑥30分位
↓
その後
◎脾臓を冷やします!
◇冷タオル
■やり方
水で絞ったタオルを、ぬるくなるまで脾臓に当てます。
■ポイント
空腹時が良い。
□こんにゃくは、〈腸の砂おろし〉とも言われています。
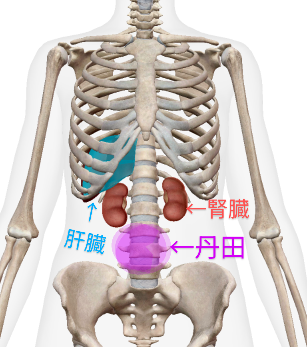
6. 胃・膵臓・脾臓の調整
胃・膵臓・脾臓は
手技にて調整をしています。
ご希望の方は、お声かけください(◕ᴗ◕✿)
Emi